この記事の目次
作成が進むBCP
皆さんの会社ではBCPを作成済みですか?
BCPとは災害時に利用する事業継続計画のことです。平成29年度に内閣府防災担当が実施した調査によると、アンケートに回答した大企業、中堅企業、その他企業の1985社のうちBCP計画策定済みの割合は大企業では64.0%、中堅企業は31.8%に達しているとのことです(「平成 29 年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」(報告書はこちら)より引用)。
水害向けBCPの整備率
ただし実態調査に回答した企業全てが水害を想定としてBCPを作っているわけではありません。報告書によると、水害をリスクとして想定している企業は大企業で43.2%、中堅企業で30.0%、その他企業で27.0%という具合だそうです。
立地的に水害のリスクはないので含めていないのだけならいいのですが、「水害リスクがよく分からないから含めなかった」というのでしたら問題です。実態調査の中ではなぜ水害をリスクとして捉えなかったのかまで質問していないため詳細は判別できませんが、ハザードマップや過去の災害履歴などで関係箇所(事業所の立地場所だけではなく、流通や従業員の通勤経路等も含む)で水害の危険性があるのであれば、ぜひ水害向けのBCPも整備していただければと思います。
初動確保の際にも防災情報が肝
さて、水害のBCPを実践的なものにしていく際にも防災情報の利用に精通しておくことが必要です。例として中小企業庁が公開している「中小企業BCP策定運用指針」(リンクはこちら)の中から、水害を対象とした初動体制のワークフローを取り上げてみましょう。
下の初動体制部分のフローを見ると「気象・水位情報等の収集(インターネット、テレビ、ラジオ、自治体等)」が一番上に位置しています。そうした情報に基づき「将来的な被災の危険性(土砂災害、浸水)」を見抜くとされています。そして危険性がある場合には、「従業員の帰宅準備」や「要援護者等の優先帰宅」などの行動が発生していきます。
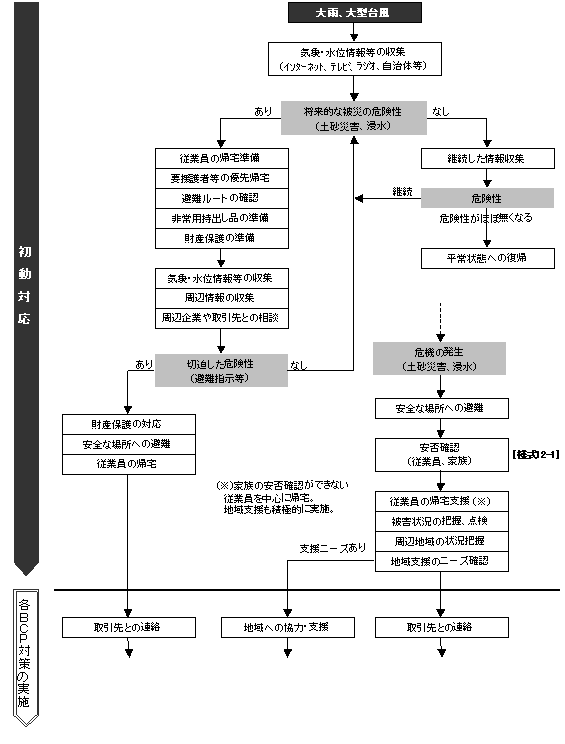
防災情報を読み解くことができるかということが、全ての初動対応のトリガーになっていることに注目してください。情報収集と収集した情報に基づいた判断の部分が満足に機能しないと、その後のアクションも機能しないことをこの図は暗に物語っています。
「見ればわかる」というけれど
中小企業庁作成の「中小企業BCP策定運用指針」では、風水害に対応するためのポイントとして、「情報源や情報の把握手段を把握することが重要」と挙げています。
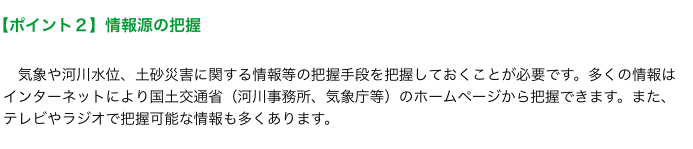
実はこれは防災情報へのアクセスだけに着目した考え方で、「情報は見れば分かる」ということを前提としています。ただ、情報を見てすぐに分かるのは信号機ぐらい情報がシンプルであれば可能でしょう。赤、黄、緑が意味することは明白です。しかし防災情報が伝えることはもっと複雑で多岐に渡っているため、見るだけ・情報源にアクセスするだけでは判別がつかない可能性があります(参照記事「防災情報とは」)。
水害向けBCPの盲点
「中小企業BCP策定運用指針」(リンクはこちら)の中では残念ながら防災情報の具体的な種類の解説や情報発表のタイミングに応じた行動の整理まで行なっていません。防災情報の利用がしっかりと整備されていないと、それは水害向けBCPの盲点になります。
皆さんがBCPを整備済みでしたらもう一度防災情報の部分を見直してみてください。これから水害向けのBCPを策定する場合は、誰が何をみていつどう判断するのかということまで整理しておくことをお勧めします。そうすることで、せっかく水害向けのBCPを作成しても、防災情報を生かした初動体制づくりまで踏み込んでおかなければBCP計画は絵に描いた餅になってしまったという事態を避けることができます。