この記事の目次
BCP作成とハザードマップ
水害向けのBCPや水害対策マニュアルを作成するときの最初のステップとして提唱されているのが、ハザードマップを見て地域の危険性を把握することです。例えばこちらの資料は兵庫県が作成した「水害から自分たちの会社をまもるために」という冊子から抜粋した説明文です(PDFのダウンロードはこちら)。まずはハザードマップで被災が起こりうる場所を確認しておいて、浸水しない地域にバックアップ拠点を作ると良いということを打ち出しています。

隠れている問題点
ハザードマップを見て安全なところを選び対策を取っていくという流れには一見何も問題がないように見えますが、実はこの兵庫県の説明の中には問題が含まれます。
冊子の中から説明文を抜き出したものが次のものです。特に問題がある部分には下線をつけています。
「水害は堤防決壊箇所から下流域の広大な地域で面的に発生しますが、全く無被害の地域も存在するため、あらかじめ洪水ハザードマップなどで事業所の被災リスクを把握する必要があります」(兵庫県作成「水害から自分たちの会社をまもるために」より抜粋)
皆さんもぜひ、何が問題か考えてみてください。
水害を限定して考えないこと
この説明の場合、「水害は堤防決壊箇所から下流域の広大な地域で面的な発生」とあるとおり、河川が決壊した場合のみに水害を限定しています。
しかし、雨を原因とする水害には外水氾濫と内水氾濫があります。河川の越水や決壊に伴う水害は外水氾濫、降った雨が処理しきれずに発生するのが内水氾濫です。この資料では内水氾濫のリスクが抜け落ちてしまっています。
兵庫県の冊子の中では「10cmの浸水でも、床に置いたパソコンは故障し、データが読み出せなくなります」という被害を指摘しています。内水氾濫でも10cmの床上浸水というのは場所や条件によって現実的に起こり得ますので、外水氾濫のハザードマップに加えて内水氾濫のハザードマップや浸水実績を確認してリスクを調べた方が良いでしょう。
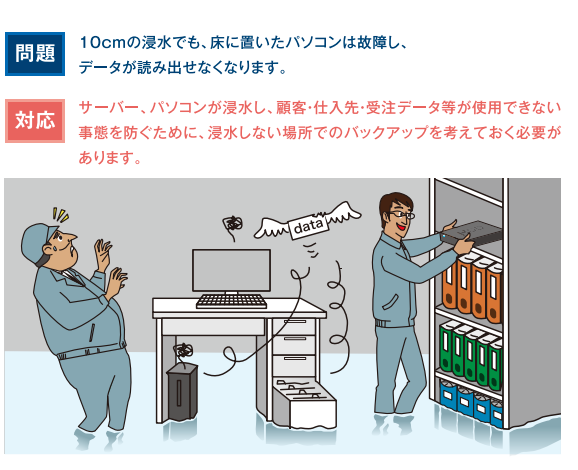
(「水害から自分たちの会社をまもるために」(兵庫県作成)から引用)